魚の体表に赤く化膿したような傷はありませんか?
それ、「ビブリオ病」です。そのままにしておくと魚が息絶えてしまいます。
「ビブリオ病」とは何か。治療法は何かを解説します。
症状・対策
大きく分けて「外傷型」と「内臓型」があります。
外傷型の初期の症状としては白っぽい丸い傷のようなものです。
その傷が次第に大きく、赤くなります。そのまま進行すると息絶えてしまいます。
外傷型は水槽内のライブロックや魚同士の喧嘩による傷に悪い細菌が入り込むことで発症します。
内臓型は外見からは判断がほぼ不可能です。
内蔵型は悪い細菌が繁殖した汚れを吸い込んでしまうことで発症します。
どちらにしても、水槽内を清潔に保つことが予防として大切です。
治療法
残念ながらかなり進行してしまったら治療は困難となります。
ですが、初期段階であれば治療可能です。
外傷型の場合、薬浴をしましょう。
薬浴は吸収性の高い「グリーンFゴールド顆粒(GFG)」の使用がおすすめです。
薬浴の際はビブリオが発症している魚を別の水槽に移して行うようにします。
また、混泳する魚がいる場合、メインの水槽もGFGを使用して全体的に消毒しましょう。
内蔵型の場合、ラクトフェリンを与えて自己治癒能力を上げましょう。
予防
予防法としては水槽を清潔に保つことです。
魚の免疫を上げるために薬を投与するのもよいですが、コストがかかります。
水槽内を清潔に保つのは魚のストレスを軽減させる効果や悪い細菌の繁殖を防ぐことにもつながります。
そもそも、水槽内の病原菌を0にすることは不可能なので、やはり繁殖を防ぐことが予防につながると考えます。
水槽内を清潔に保つためには以下の方法がおすすめです。
①水流ポンプを設置する
②こまめな掃除
水流ポンプを設置する
水流がないと水が淀んで汚れが溜まりやすくなり病原菌が繁殖してしまいます。
なので、水槽には水流ポンプが必要です。
水流ポンプについては別の記事でまとめているので参考にしてみてください。

こまめな掃除
餌や糞が病原菌が繁殖する原因となります。
海水魚水槽の場合、水替えをすると水槽内のバクテリアが減少してしまうので掃除のし過ぎはよくありません。
ですが、餌や糞が目立って残るようであればこまめに掃除をして水槽内の環境を整えてあげましょう。
まとめ
・ビブリオ病は外傷や口・エラから病原菌が入り込むことで発症する
・早期治療は外傷の場合は薬浴、内臓の場合は薬を食べさせる
・予防策として水槽をきれいに保つ
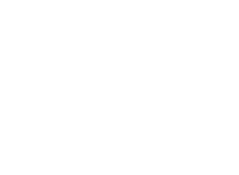





コメント